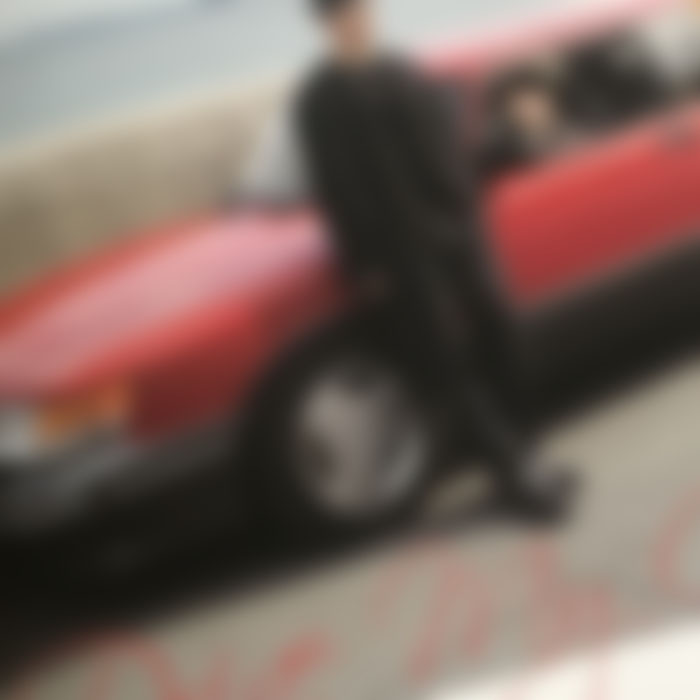時間をやりくりして、2021年9月2日、TOHOシネマズ新宿で、濱口竜介の『ドライブ・マイ・カー』を観る。濱口の映画は何本か観ており、どれもたまらなく好きなのだが、この映画には思わず感動してしまった。
どこがと言われても整理して書くのは難しいのだが、私は彼の「話法」が好きだ。もちろん物語そのものも魅力的なのだが、それ以上に、その物語をどう語るのか、その語り口が好きでたまらない。完璧に出来上がった物語を、まるで謎解きでもするように手際よく記述していくのではなくて、揺れ動き続ける関係を極めて丁寧に記述していく。極端に言えば、ここには揺れ動く関係性しかないような印象さえ持つこともある。物語の結末が主要な関心事ではない。いやそもそも、映画は一応終わるのだが、ここで語られた物語りは終わることなくずっと続いていく。私たちの人生の物語りが起承転結もなく、終わることもなく続いていくのと同じことだ。だからだろう、彼の映画を観てずっと時が経つのに、時々、あの登場人物はいまどうしているんだろうと、まるで友人か特別な人を思い出すように、気になることも多い。
『ドライブ・マイ・カー』はまず、俳優であり斬新な演出家でもある家福と、寡黙な雇われ運転手みさきというシチュエーションが実に良かった。喪失と再生、いや喪失感との折り合いの付け方を人が獲得していくまでの物語と言ってしまえばいいのだろうが、その魅力は細部に散りばめられていて、圧倒的な説得力に満ちていた。
ちょうど7月に現代アートチーム《目》が実行した『まさゆめ』を経験していたからか、私は特に沈黙とか寡黙さに強く反応したのかもしれない。困難に直面した人に対して、往々にして慰めの言葉や鼓舞する言葉を饒舌に投げかけがちだけれど、自分自身の経験からしても、寡黙に寄り添うことこそが大きな力を持つことは多い。
しかしそういえば、『ドライブ・マイ・カー』を話すことと話さないことにまつわる物語と捉えてみることもできるかもしれない。今晩話したいことがあると言って、それを言わぬまま突然この世を去った妻、音。あるいは映画のなかで展開する『ゴドーを待ちながら』や『ワーニャ伯父さん』といった演劇の制作シーン。セリフ、セリフ、セリフ。しかも家福の演出は多言語なのでさまざまな言葉が飛び交う。その中には手話さえ含まれる。イ・ユナは韓国手話で話し、無言で役を演じていく。ドライバーとして雇われたみさきはいたって寡黙。いや、寡黙に寄り添うということなら、家福の愛車を置いて他にない。
映画に描かれた演劇の制作シーンは実に魅力的だった。感情を込めず、ただただ台本を何度も棒読みさせていく演出方法は、神戸KIITOで『ハッピーアワー』がつくられていく時、この目で目撃してきたことだったから、ここまで企業秘密を公開してしまっていいのだろうかと、私自身が心配になるほどのリアルさだった。それに今回はここに多言語が導入されて、なんとも心弾む状況が生み出されていく。
蔡國強と『万里の長城を10,000m延長する』の実現可能性を調べるために、北京に赴いた時のことだ。蔡の友人である中国政府の外交官と福建省出身の女性、そして蔡と私の4人で会議を持った。話も弾んで、今は蔡と福建の彼女が熱心に話している。
その時外交官の彼が笑いながら、小声で私に英語で囁く。「実は彼らが何を話しているのか、私にはさっぱりわからないのです」。それで理解したのだが、この4人の会話は実に奇妙なものだった。外交官が話せるのは北京官話、つまりマンダリンと英語。福建省の彼女が話せるのはマンダリンと福建語。蔡が話せるのはマンダリンと福建語と日本語。そして私は日本語と英語。今、蔡と彼女は福建語で話している。まるでタモリの四カ国語麻雀のような状況で、4人が同時に理解できる話し合いはない。かなり面倒で、実際は大変な苦労を強いられるのだが、私はこういう多言語が飛び交う状況が好きでたまらない。そう言えば、P3の現場でもこういう状況、時々生まれていたなあと、懐かしく思い出す。
実は好きなシーンは多過ぎて、語り始めたらきりもなく、飲み屋で続くファン話になりかねないから深入りはしないけれど、映画のラスト、韓国の道路ぎわの駐車場に佇むみさきの姿が印象的で、忘れることができない。横には家福の車だった赤のサーブ900がある。なぜかこのシーンを見た途端、私自身もこれでよかったとすごくほっとして、ある種の喪失から立ち直れたような気になったものだ。説明もつかない、素晴らしいシーンだったと思う。
しかしなぜ、私はこうまで濱口竜介の映画に惹きつけられていくのだろう。『ドライブ・マイ・カー』と並行してつくられた彼のもう一本の映画『偶然と想像』を観て、そうか!と思った。これは第一話「魔法(よりもっと不確か)」、第二話「扉は開けたままで」、第三話「もう一度」という3編からなる短編集で、第71 回のベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞した作品だ。インディペンデントで制作されたからか、よりフットワークも軽くつくられているが、私はこの作品にも強い衝撃を受けた。そう、それこそこの映画のタイトルになっている偶然と想像とは、自著『別府』では「たまたま」という言い回しで書いたのだが、まさに私自身の主要な関心事にほかならなかったからだ。生きていくこと、自分の人生にとっての主要な駆動力であり、創造の源泉ではないのかとさえ思っている。
さらに濱口竜介はあるインタビュー[1] で、「濱口監督にとって、映画とは?」という質問に対して、次のように答えている。
「結果的にはもう一つの現実を作るということだと思います。この現実をもう一つの現実に分岐させていくというほうが、今感じていることに近いかもしれない。こういう現実もありえるのではないか、と。それは自分たちの現実を照らす鏡のようなものになるんじゃないかと思っています」
ここで映画をアートに置き換えれば、いかにも私自身が言いそうな言葉である。おそらく、私が彼の映画に強く惹きつけられる理由はここにある。
(2022/2/5)
[1]2021年7月31日 朝日新聞フロントランナー